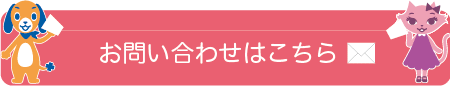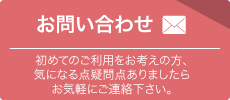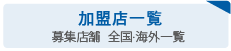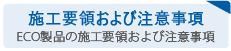更新日:2017. 4. 15.
固体の電子の光励起と光触媒反応
光触媒になるものには、大別して光があたると電気伝導を生じる物質(光伝導物質)と半導体、および色素(有機金属錯体)があります(先に書いたクロロフィルはマグネシウムの錯体です)。酸化チタンは、そのままでは光伝導物質ですが、半導体にもなります。ここでは酸化チタンについて説明します。
図5 光による固体中の電子のバンドギャップ励起 酸化チタンの結晶は、そのままでは電気を通しませんから、絶縁体です。ところが、波長が400nm以下の紫外線を当てると、電気をわずかに通すようになります。これを光伝導といいます。光伝導はなぜ起こるのでしょうか。
固体の中の電子は、エネルギーが同じくらいの電子が集まって、エネルギー帯というものをつくっています。絶縁体の電子はすべて価電子帯と呼ばれるエネルギー帯に属しています。価電子帯の電子は完全に詰まっており、動くことができません。電気伝導は、電子が動くことによって起こりますから、この状態では電気が流れません。
価電子帯よりエネルギーの大きいところに、伝導帯というエネルギー帯があります。価電子帯の上端と伝導帯の下端のエネルギーの差をバンドギャップエネルギーといいます。
価電子帯の電子が、バンドギャップより大きなエネルギーを持つ光を吸収すると、伝導帯に上がることができます。光触媒として使われている酸化チタン(アナタース型)は、バンドギャップエネルギーが3.2eVなので、上の式を適用すると、波長が390nm以下の光を吸収することがわかります。
伝導帯に上がった電子は動くことができるので、電気伝導が生じます。これを光伝導といいます。一方、価電子帯には電子の抜け跡ができます。これは、マイナスの電荷が抜けたのでプラスになったと考え、正孔(hole、ホール)と呼びます。これらの電子と正孔が光触媒反応を起こすことになります。
ここで注意しなければならないことは、光で電子が励起されてもエネルギーが変わっただけであり、空間的位置は動いていないということです。そのままでは電子と正孔はマイナスとプラスの電荷なので再び結びついて(再結合という)元の状態に戻ってしまいます。光触媒反応が起こるためには、電子と正孔の寿命が長い必要があります。酸化チタンは、この寿命がながいので光触媒として使うことができます。
関連記事
-
● ①光触媒と②無光触媒の2つの触媒で安心・安全

VOC・ウイルス・細菌・花粉・臭い・ダニ等を分解除去 小さなお子様がいらっしゃるご家庭におススメです 居室空間リノベーションとは? ナショナルリファインは、居室内の生活空間において ① …… -
● 無光触媒について

触媒とは 「⾃⾝は変化することなく、ほかの物質の反応速度を促進する物質」と定義されます。 光触媒とは 「太陽光や蛍光灯などの光(紫外線)を浴びると触媒として働く物質の総称」と定義されます。 代表的な…… -
● \ What’s /エアークリーンコーティング

365日24時間休むことなく空気をリフレッシュ! 「四塩化チタン」をリン酸等と反応させることにより「リン酸チタニア」が主成分の画期的な機能性コーティングです。 「リン酸チタニア」は、空気中に含まれる水分……